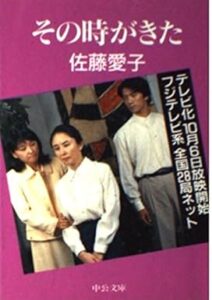その時がきた(1997)の感想
1970年に婦人公論に佐藤愛子が連載した小説の3回目のドラマ化。
前の2回は原作完結後すぐの1972年(南田洋子と小野寺昭)、1982年(小山明子と寺泉憲法?)、そして本作が1997年、大谷直子と増沢望である。
「ツィゴイネルワイゼン」であれほど艶かしかった大谷直子は本作当時47歳、劇中ヒロインとほぼ同じ設定。今なら美魔女というかどうか、年相応にリアルで身持ちも固そうなので、56話もあるこのドラマで増沢某(この人のことは知らない)とどうかなるようにはとても見えない。三角関係になるらしい娘は宮沢美保(ホーチャンミという謎の別名をもつ女優)。この人は今でもよく見る。
そもそも原作(中公文庫だが5000円以上の値がついている)のヒロインは45歳で、これは中年女性の話だから微妙に違う。そして中年女性というカテゴリーが今ではなくなってしまったようにも思う。「その時」って一体何なのか? 閉経?
その時がきた(1997)あらすじ
より美しく、いつまでも若くありたい女性たちの願いを叶える美容外科の世界で、美容外科医として働く九重彰野(大谷)は、アルコール依存症の治療のため城ケ島の診療所に籠る夫の明治(岡本富士太)と、美術大学に通う21歳の娘・毬世(宮澤)の3人家族で生活を送っていた。
朝から休むことなく働いている彰野は48歳。他の医師からは「まだ48なんだから、家族のことばかりではなく自分の楽しみを見つけなさい」と助言を受けていた。その頃、毬世は大学のグループ展で、彰野を描いた自分の絵を見つめる一人の男性に気付く。その男性は毬世の絵を見て「きれいだけど寂しそうだ」と呟き、さらに毬世に「この人物は実在するのか?」と尋ねるのだった――。
一方、彰野のクリニックには常連の女性患者が訪れ、目元のシワを取ってほしいと訴える。彰野は「また恋でもしたの?」と尋ねるが、患者は「誰かのためでなく、このまま若さを失うのが耐えられない」と嘆く。そんな女性に彰野は、「どんなにジタバタしても、老いていく“その時”はやって来る」「一時的に若さを保っても、老化を防ぐことにはならない」と諭した。
その翌日、彰野のもとにアルバイト希望の医師が面接にやって来て――。
その時がきた 見どころ
- 熟年女性の心情とリアルな葛藤
48歳の美容整形医・彰野の「若さを保ちたい」という焦りや、夫のアルコール依存・娘との関係に揺れる心情が丁寧に描かれている。市野直親プロデューサーも「女性の生きる時間を鮮明に表現した」と評価している。 - 禁断の恋と年齢の壁
年下のアルバイト医・添田との出会いが彰野の人生を大きく揺さぶり、「熟年の恋」というセンセーショナルな展開が深いドラマ性を生み出している。 - 豪華で実力派のキャスト陣と演技派の演出
大谷直子をはじめ、増沢望や宮澤美保など豪華キャストが揃い、清水喜美子脚本+中谷正和・藤木靖之ら複数演出体制によって、昼ドラながらテンポと濃密さのバランスが秀逸。 - 社会的テーマの先進性
美容整形、熟年離婚、年下との恋…当時では斬新だったテーマが散りばめられ、現在でも共感や衝撃を呼ぶ内容。 - 第一話からの導入力とドラマ全体への引き込み
第1話では彰野の仕事ぶりや家族関係、謎の若者との出会いなど、物語を強く引きつける要素がふんだんに盛り込まれている。
その時がきた(1997)キャスト
その時がきた(1997)スタッフ
プロデューサー:風岡大、平野一夫、小池唯一
脚本:清水喜美子、梶本恵美
音楽:岩本正樹
音楽コーディネーター:細井虎雄
技術:湯本秀広
撮影:山岸桂一
照明:荒井徹夫
音声:小高康太郎
VE:高梨剣
VTR:渡部営
編集:大塚民生
選曲:山本文勝
音響効果:江連隆太郎
整音:松本能紀
デザイナー:金子幸雄
美術進行:常盤俊春
大道具:手塚常光
装飾:亀岡紀
小道具:及川幸恵
持道具:津田季美
衣裳:中村美保
ヘアーメイク:山内聖子
医事監修:大塚美容形成外科
技術協力:バスク
スタジオ:東京メディアシティ・TMC-1スタジオ
制作会社:東海テレビ、泉放送制作
過去の「その時がきた」
1972年版
1972年9月18日 – 12月1日に東海テレビの15分昼ドラマ枠にて放送。
キャスト
スタッフ
1982年版
1982年1月6日 – 3月26日に毎日放送「妻そして女シリーズ」枠にて放送された。