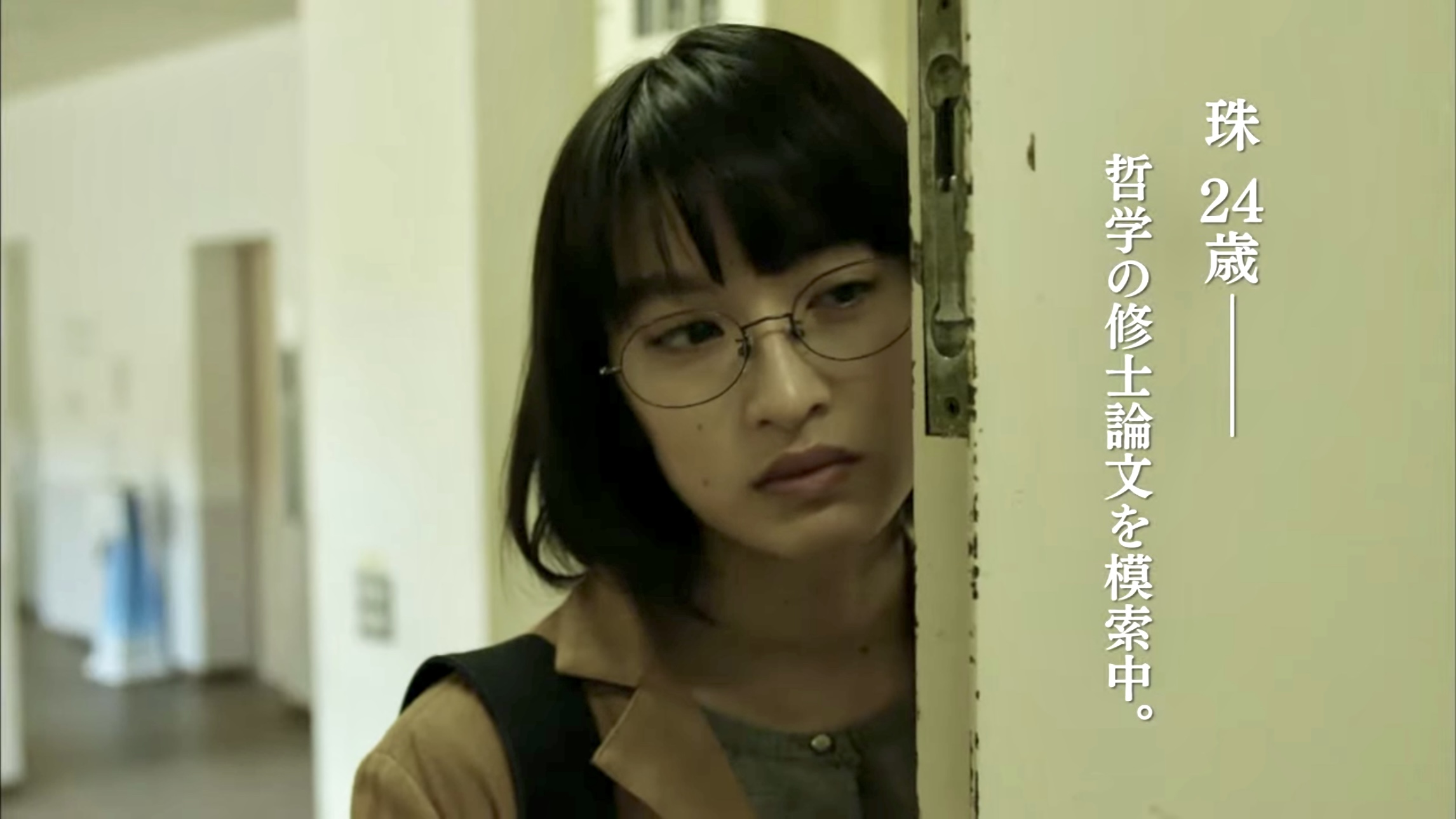まだ観ていない方は、Amazon Prime Videoで今すぐ視聴できます。
哲学とそこからはみ出る烏丸せつこ(二重生活の感想)
哲学科の院生門脇麦は、リリー・フランキーの教授の勧めで、修士論文を書くために見知らぬ人の「尾行」を決意する。という出だしからして荒唐無稽で、小学生かよと思ってしまうが、このくだりは「本当の話」(今は古本でしか入手できない)を書いたソフィ・カルがボードリヤールにそそのかされたのと同じ構図ということになる。
ソフィ・カル「本当の話」
ソフィ=門脇が選んだターゲットは近所に住む妻子持ちのエリート編集者(長谷川博己)で、ブックデザイナーと重ねる不倫の逢瀬や修羅場を門脇は目の当たりにする。マイクオフで会話などよく聞こえないまま(門脇は興味がないのでイヤホンをしている)の尾行の描写は、ドキュメンタリー畑の監督らしい、本作のメインをなす異常な画面となっており、それなりに興味深い。
安部工房を読んだことがある人なら、尾行に気づいた長谷川と門脇が共犯関係に陥っていく展開を期待するところだ。しかしそういう展開にはならず、なぜ尾行をやめられないのかという門脇の告白を、長谷川は「どこにでもある話だ。陳腐だ」と喝破し、あくまでも凡庸な編集者であることが強調される(全共闘世代の小池真理子の原作(未読)では、ヒロインと編集者は飲み仲間になるそうなので、やはり共犯関係の線だろうと想像する)。
リリー・フランキーの内面が描かれている点も原作とは異なる。映画では、金で雇った妻を同道して危篤の母親を見舞ったりするフシギな行動をとっているのだが、そうした行動の意味や、その挙句に自殺を試みる心の動き、そもそもなぜ門脇に尾行を勧めたのかといったことも、映画はほとんど説明しない。ドキュメンタリー畑の監督ならではのやり方で、あるがままの画面の力で押しきるのだ。
烏丸せつこのアパートの管理人が画面からはみ出る存在感で、コワかった。
二重生活 見どころ
ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーの概念である「現存在(ダーザイン)」をテーマに、他者を尾行することで自己を見つめ直していくという哲学的で心理描写の深い映画。
- 「尾行」を通して自己を見つめるという異色のテーマ
大学院で哲学を学ぶ学生・珠(門脇麦)は、指導教授の篠原(リリー・フランキー)から「対象を決めて、その人を徹底的に尾行し、その人のことを記録する」という「哲学研究」を勧められる。珠が選んだのは、隣人である石坂(菅田将暉)の尾行だった。この映画のユニークな点は、単なるサスペンスとしての尾行ではなく、他者の日常を覗き見ることで、自分自身の存在や人生の意味を問い直すという内省プロセスが描かれていることである。 - 門脇麦の繊細かつ危うい演技
珠の複雑な内面、好奇心、尾行という行為にのめり込んでいく危うさを、門脇麦さんが抑制された中にも熱のこもった演技で表現。視線や表情の変化が珠の心の揺れ動きを巧みに伝える。 - 菅田将暉の魅力的な存在感
珠の尾行対象となる石坂を演じる菅田将暉は、ミステリアスでありながら、どこか人間的な魅力を放つ。彼の存在が珠の「二重生活」に刺激を与え、物語の緊張感を高める。石坂の「もう一つの顔」が明らかになっていく過程もスリリング。 - 哲学的テーマの深さ
ハイデガーの哲学概念をベースに、「人は他者を通して自分を知る」というテーマが描かれる。他人の生活を追うことで、自分自身の孤独や、本当の自分を見つけることの難しさ、「生きる」ことの意味を問う映画。 - 日常に潜む非日常と緊張感
派手な事件は起こらないが、日常の風景の中で「尾行」という非日常的な行為が行われることで、常に静かな緊張感が漂う。尾行がバレそうになる瞬間、珠が石坂の秘密に触れていく過程がスリリング。 - 監督・岸善幸のリアリズム
ドキュメンタリー出身の岸善幸監督が手掛けており、物語にリアルな質感を与えている。日常の何気ない風景や会話の中に、哲学的な問いや人間の闇を垣間見せる手腕が光る。
映画「二重生活」における珠の行動とハイデガー哲学
この映画は、マルティン・ハイデガーの主要な哲学概念「現存在(ダーザイン)」と「現存在のあり方としての現存在の現れ(他者との関係性)」を示唆的に描いている。
ハイデガーは、「人間(現存在)は、世界の中に『投げ込まれた』存在であり、常に他者との関係性の中で自己を認識し、その本質的なあり方(本来の自己)を追求する」と考えた。
本作における珠の「尾行」という行動は、この哲学を具体的な形で探求する試みとして描かれている。
- 「非本来的な自己」からの脱却と、他者への注目
映画が始まる時点での珠は、大学院生でありながら、自分の存在意義や将来に漠然とした不安を抱え、どこか宙ぶらりんな状態にある。ハイデガーが言うところの、社会の「世人(ダス・マン)」の中に埋没し、他者の目を気にしながら生きる「非本来的な自己」の状態に近いと言える。
彼女は自分の内面を見つめることができず、あるいは見つめることに抵抗があるため、教授の提案に乗って「他者」である石坂の尾行を始める。この行動自体が、自分の内側ではなく、あえて外側(他者)に目を向けることで、何かを見つけようとする試みである。 - 他者の「現存在」を追体験する試み
珠は石坂を尾行し、彼の日常、彼の仕事、彼が会う人々、彼の生活空間などを詳細に観察し記録する。これは石坂の「現存在」を追体験するかのように追いかける行為である。石坂がどう行動し、何を感じ、どんな関係性を持っているのかを覗き見ることによって、珠は彼の「世界の中での存在」を間近に感じ取ろうとしている。 - 他者の「闇」に触れることで、自己の「闇」を認識する
当初、石坂はどこにでもいる普通の隣人に見えるが、尾行を続けるうちに、彼が抱える秘密や、一見すると「よくない」と感じられるような彼の「二重生活」が明らかになっていく。
石坂の生活に潜む「闇」や矛盾に触れることで、珠は自分が抱える葛藤や、目を背けてきた自分自身の「闇」にも気づく。他者の不完全さや複雑さを目の当たりにすることで、自己の不完全さや複雑さも許容できるようになる、あるいは認識せざるを得なくなる。 - 他者の「あり方」が、自己の「あり方」を浮き彫りにする
石坂の生活や人間関係、彼が時に見せる感情の動きは、珠自身の生き方や人間関係を映し出す鏡になる。
例えば石坂が特定の人と会う様子、彼が抱える問題に触れることで、珠は自分自身の恋愛観、家族との関係、友人との付き合い方などについて考えさせられる。
ハイデガーは、「現存在は他者と共に存在している」と述べ、他者との関係性の中で、初めて自分自身の「可能性」や「限界」が明確になるとした。
珠は石坂を尾行することで、彼という他者の存在を通して、自分の人生における選択肢や、今まで気づかなかった自分自身の性質、あるいは避けてきた問題に直面する。 - 「見る」行為から「関わる」行為への変化
尾行という行為は、最初は対象から距離を置き、客観的に「見る」ことから始まる。
しかし、映画が進むにつれて、珠は石坂の生活に深く入り込み、時には直接的な形で関わってしまう場面も出てくる。
この「見る」だけの受動的な行為から、意図せず「関わる」という能動的な行為への変化が、珠自身の「現存在」のあり方を揺り動かし、彼女自身の人生を動かしていくきっかけになる。
他者に深く関わることで、自分もまた他者から影響を受け、変化していく、という相互作用が描かれる。
「二重生活」における珠の「尾行」という行動は、このように、単なるミステリーやサスペンスに留まらず、ハイデガーの哲学が問いかける「人間が他者とどう関わり、その中でいかに自己を認識し、本来の自己へと向かうのか」という深遠なテーマを、具体的な物語として表現していると言える。
参考図書
本書は、、可能な限り日常の日本語で『存在と時間』を理解することを目指します。章立てに従って、原文を忠実に読解した上で平易な日本語で解説して行きますので、翻訳書で『存在と時間』を読むよりもはるかに容易にその内容を理解することができます。また、なぜハイデガーはこの書を完成させることができず、未完のままに終わったのか、その「限界」についても、本書を読み進めていけば、おのずと理解できるでしょう。
二重生活 あらすじ
大学院の哲学科に通う珠は担当教授の篠原から、修士論文のテーマとして、ひとりの対象を追いかけて生活や行動を記録する“哲学的尾行”の実践を持ちかけられる。理由なき尾行に戸惑う珠だったが、書店でマンションの隣の一軒家に美しい妻と娘と共に住む石坂を発見。作家のサイン会に立ち会っていた彼を尾行しようとする。
二重生活を観るには?
二重生活 キャスト
二重生活 スタッフ
『二重生活』は、静かで重層的な人間ドラマです。この記事で少しでも興味を持たれた方は、ぜひ本編をチェックしてみてください。
二重生活の原作(小池真理子)
大学院生の珠は、大学時代のゼミで知ったアーティスト、ソフィ・カルによる「何の目的もない、知らない人の尾行」の実行を思い立ち、近所に暮らす男性、石坂の後をつける。そこで石坂の不倫現場を目撃し、他人の秘密に魅了された珠は、対象者の観察を繰り返す。しかし尾行は徐々に、珠自身の実存と恋人との関係をも脅かしてゆき――。渦巻く男女の感情を、スリリングな展開で濃密に描き出す蠱惑のサスペンス。 解説・野崎歓