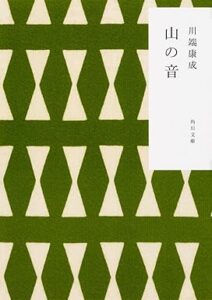山の音の感想
やはり唐突なこの鼻血のシーンこそ、原節子という女優の極致なんじゃないかという気がする。
原は体調不良を理由に座り込み、山村聡が近づくと、白いハンカチで鼻を押さえながら軽く笑みを浮かべる。
白は純粋無垢、赤は情念や生命。この対比は「隠された情欲の兆し」ならん。
カメラは信吾と菊子の距離を詰め、息遣いが伝わるような親密さを演出する。
原は状況の微妙さを知りながら、あえて微笑む。これが無意識下の挑発にも見え、観る者に複雑な印象を与えてしまう。「この女は本当に無垢なのか?」と思うのだ。
川端康成と谷崎潤一郎ではその変態性が異なるが、成瀬は、ほんらい変態性とは遠い存在だと思う。
山の音の見どころ
川端康成の原作は、老境の孤独と性の微光を表現した小説である。
老いた父・尾形信吾が、戦争未亡人となった嫁・菊子への淡い思慕を抱きつつ、息子の不実や家庭の冷えを見つめる。声高な情念ではなく、“心の奥底で小さくさざめく欲望と後悔”がそこにある。
「山の音」とは、文字通り山からの響きのことだが、それは老いゆく信吾の心に忍び寄る死の気配、過去への追想の象徴でもある。
川端は“静寂の音”という矛盾の中に人間の感情の複雑さを封じ込めた。
成瀬はこの川端的な繊細さを、カメラの緩やかなパンと固定ショット、人物の沈黙や視線のズレで映像化している。
たとえば菊子(原節子)の微笑と沈黙。彼女の存在が、老父・信吾(山村聡)にとって慰めと禁忌の両方を帯びる。また窓外の庭木や遠景の山は“老境と死の訪れ”を暗示している。
川端文学は「語らないことで語る」文体が特徴である。成瀬はそれを不自然なほど長いカットと人物の間合いで映像化している。観客はセリフよりも空気感や沈黙の重さから登場人物の心情を感じ取らねばならない。
この「余白の演出」によって、成瀬は川端の文体を損なわずに映画へ移植した。
原作での信吾は、老いを悟りながらも、時に湧き上がる性的衝動に戸惑いを見せる。成瀬はこの微妙な心理を、山村聡の落ち着いた表情と所作で表現している。エロスとタナトス(性と死)が静かに同居する空気感は、川端文学と成瀬映画の双方の核となっている。
原作では信吾は自身の老いを痛感し、人生の終焉を予感し、菊子への淡い恋慕は成就しないものの、彼女を介して「生の微光」を味わった満足感を感じながら、「山の音がまた聞こえた。」という一文で終わる。死の足音と同時に自然への回帰を暗示する終わり方だ。
これに対し、映画では菊子は病気療養のため信吾の家を去る。信吾は一人残され、空虚な家に佇む姿がラストカットとなる。原作の「自然と共に生き死す」という詩情は薄まり、より現実的で冷たい孤独が強調されている。
成瀬は最後の最後に川端の余韻を捨て、観客に老いの現実と冷たさを直視させたのだ。
山の音の原作のあらすじ
尾形信吾は、妻・保子、長男夫婦(修一、菊子)と共に鎌倉で暮らす。最近、もの忘れや死への不安を感じるようになった信吾は、嫁の菊子に淡い恋情を抱く。菊子は信吾の優しさに親しみを感じ、信吾にとっては家族の重苦しさの中の「窓」だった。修一は浮気をしており、信吾は菊子を不憫に思い、別居を勧めるが、菊子は修一の帰りを待つことを選ぶ。修一は戦争トラウマを抱え、菊子を軽んじる言動に信吾は怒りを覚える。信吾は、菊子への想いと家族の複雑な関係の中で、死や老いへの不安と向き合う。
山の音を観るには?
山の音のキャスト
尾形修一:上原謙
尾形信吾:山村聡
尾形保子:長岡輝子
谷崎英子:杉葉子
池田:丹阿弥谷津子
相原房子:中北千枝子
相原:金子信雄
絹子:角梨枝子
信子の友人:十朱久雄
事務員:北川町子
房子の娘:斎藤史子
巡礼:馬野都留子
山の音のスタッフ
製作:藤本真澄
原作:川端康成
脚本:水木洋子
音楽:斎藤一郎
撮影:玉井正夫
美術:中古智
録音:下永尚
照明:石井長四郎
編集:大井英史
チーフ助監督:筧正典
製作担当者:馬場和夫
特殊技術:東宝技術部
現像:東宝現像所
山の音の原作(川端康成)
老いを自覚し、ふと耳にした「山の音」を死期の告知と怖れながら、息子の嫁に淡い恋情を抱く主人公の様々な夢想や心境、死者の夢を基調に、復員兵の息子の堕落、出戻りの娘など、家族間の心理的葛藤を鎌倉の美しい自然や風物と共に描いた作品。繊細冷静に捕えられた複雑な諸相の中、敗戦の傷跡が色濃く残る時代を背景に〈日本古来の悲しみ[2]〉〈あはれな日本の美しさ〉を表現した。戦後日本文学の最高峰と評され、川端の作家的評価を決定づけた作品として位置づけられている。